大切にしてきた指導方針
剣道に限らず武道には型がある。
型や基本を疎かにして試合で勝つ事を重視するあまり、高校生あたりで成長が止まってしまい苦しむ子供達を見てきた。
その経験から子供達の剣道指導は、基本を重視する方針で行なってきた。
しかし、学生時代の剣道は試合が中心。小学校、中学校、高校と剣道を続けていくには有る程度試合に勝てなければ剣道自体が楽しくなくなって辞めてしまうのも事実だ。
そこで途中からは勝利至上主義にならないよう注意しつつ、試合で勝てるような指導にシフトしていった。
そうは言っても、やはり一番気掛かりなのは、子供達が剣道を続けていき、壁にぶち当たった時に帰ってこれる基本を今のうちに身につけさせてあげたい。
基本を逸脱したテクニックではなく、しっかりとした土台にそびえ立つ高い次元の基本、『超基本』を身につけさせてあげたい。
最近はそう考えるようになった。
超基本を実現させるための段階
超基本の理想は、真っ直ぐ攻めて、相手を動かして、腰の入った力強い打突をして残心まで綺麗な一本を取り、最後の蹲踞や礼まで品がある。そんなイメージだ。
そんな事は大人の僕でも難しい。しかしそこを目標に指導していきたい。
だって僕らが真剣に取り組んでいるのは剣術ではなく、剣道だから。
高い理想はさておき、子供達がいきなりそんな高いレベルになるはずもない。
有る程度ステップを考える。
第一段階は、礼儀作法と基本打ちのレベルを高い次元にもっていくこと。これは一人稽古でもできることだ。具体的には、礼儀作法を細部まで徹底したり、基本打ちや打ち込みのスピードや姿勢、発声、打突力等を上げることだ。
第二段階では、第一段階でレベルの上がった動作を対人稽古の地稽古や試合でも出せるようにすることだ。ここでは打たれることを恐れさせないにしないと、第一段階で身についた基本が崩れてしまうので注意していきたい。
第三段階は、超基本が身についた上級生が多くなり、上級生は下級生にいい影響を与え出し、いつしか超基本が道場の文化になることだ。
そんなことをぼんやり思考していた。
全力を出せない
そこで日頃の稽古で少しずつ第一段階を意識した稽古を入れてみることにした。
先ずは短時間だが、全力での面の打ち込みを連続5本やってみた。
この打ち込みでは、全力の大きな声、全力のスピード、左足で腰ごと上半身を前に出すことによる強い打突を意識させた。
僕はこの子達が遊びの時に全力で走っているのを見ているので、有る程度型を気にせずに全力を出した時の打ち込みはイメージできていた。
しかし、やってみて愕然とした。
子供達は全力でやっているつもりだが、日頃の面の打ち込みとほとんど変化がなかったのだ。
つまり全力が出せないのだ。
冷静にこれまでの稽古を分析してみる。
型や基本を重視することは、自分の体が今どう動いているのかに注意がいく。イメージする動作に近づくように自分の体の動きに意識が向かう。
これはこれで大切なことだ。
しかし、自分の体がどう動いているのか忘れるほどフルパワーを出す稽古はあまりやってこなかったことに気づいた。
剣道的な動作ができるようになってから、次の段階としてその動作のままスピードアップさせるイメージで指導してきていたが、順番が違うことにようやく気がついた。
全力を出すことを体に覚えさせることはとても大切なことだ。
今後は全力を出すことが先、もしくは同時並行で基本にしていこうと思う。
全力を出すことが当たり前、もはやクセのように全力が出せるようになって初めて試合でも全力が出せる。
おわりに
よく教員が、子供達に教えるというより、子供達から教えてもらうことの方が多いと耳にする。
あれは綺麗ごとではなく本当のことだなと指導していて心底そう思う。
最近は子供達に全力を出すことを意識させているため、自分の稽古の時も短時間でも全力の基本打ちを意識して稽古している。
全力を出すことは以外と難しい。
「怪我するかも」とか「この後の地稽古まで体力を温存しておこう」など大人はすぐ全力を出さない言い訳をする。
自分の剣道も全力を出すことがクセになるように稽古していきたい。


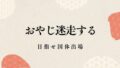
コメント